- m3.comトップ
- > DI Station
- > メファキン「ヒサミツ」錠275

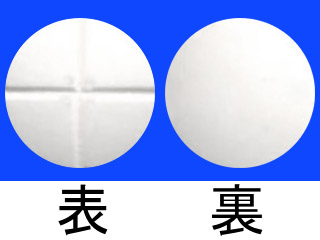
警告
-
本剤を予防に用いる場合には、現地のマラリア汚染状況も踏まえて、本剤の必要性を慎重に検討すること。[5.1、8.1参照]
禁忌
-
2.1 本剤の成分又はキニーネ等の類似化合物に対して過敏症の既往歴のある患者
-
2.2 低出生体重児、新生児、乳児[9.7参照]
-
2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5参照]
-
2.4 てんかんの患者又はその既往歴のある患者[痙攣を起こすことがある。]
-
2.5 精神病の患者又はその既往歴のある患者[精神症状を悪化するおそれがある。]
-
2.6 キニーネ投与中の患者[10.1参照]
-
2.7 ハロファントリン(国内未承認)投与中の患者[10.1参照]
効能・効果
-
マラリア
用法・容量
-
治療
-
通常成人には、体重に応じメフロキン塩酸塩として、825mg(3錠)〜1,100mg(4錠)を2回に分割して経口投与する。
-
30kg以上45kg未満
-
初回550mg(2錠)、6〜8時間後に275mg(1錠)を経口投与する。
-
-
45kg以上
-
初回550mg(2錠)、6〜8時間後に550mg(2錠)を経口投与する。
-
-
-
感染地(メフロキン耐性のマラリア流行地域)及び症状によって、成人には体重に応じメフロキン塩酸塩として、1,100mg(4錠)〜1,650mg(6錠)を2〜3回に分割して経口投与する。
-
30kg以上45kg未満
-
初回825mg(3錠)、6〜8時間後に275mg(1錠)を経口投与する。
-
-
45kg以上60kg未満
-
初回825mg(3錠)、6〜8時間後に550mg(2錠)を経口投与する。
-
-
60kg以上
-
初回825mg(3錠)、6〜8時間後に550mg(2錠)、さらに6〜8時間後に275mg(1錠)を経口投与する。
-
-
-
-
予防
-
通常成人には、体重に応じメフロキン塩酸塩として、206.25mg(3/4錠)〜275mg(1錠)を、マラリア流行地域到着1週間前より開始し、1週間間隔(同じ曜日)で経口投与する。流行地域を離れた後4週間は経口投与する。なお、流行地域での滞在が短い場合であっても、同様に流行地域を離れた後4週間は経口投与する。
-
30kg以上45kg未満
-
206.25mg(3/4錠)
-
-
45kg以上
-
275mg(1錠)
-
-
-
注意事項
重要な基本的注意
-
8.1 本剤の治療及び予防のための投与に際しては、マラリアに関して専門的知識を有する医師の指導の下で行うこと。[1.、5.1参照]
-
8.2 本剤の投与により、めまい、平衡感覚障害、精神神経障害が発現することがあるので、投与後少なくとも4週間は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、ジェットコースター等の動きの激しい乗物への乗車を避けさせること。
-
8.3 投与にあたっては経過を十分に観察し、症状に応じ治療上必要最小限の使用にとどめ、効果がみられない場合には他の療法に切り替えること。[7.2参照]
-
8.4 投与開始に先立ち、主な副作用について患者に説明し、不安、うつ病、落ち着きのなさ、錯乱又は発疹等の皮膚の異常が認められた場合には速やかに主治医に連絡するよう指示すること。[11.1.1、11.1.2、11.1.4参照]
-
8.5 本剤の投与に際しては、次のことを含めて本剤の有効性及び安全性について患者に十分説明すること。
-
8.5.1 国内においては比較臨床試験が実施されていないこと。
-
8.5.2 一般臨床試験において、少数例で有効性と安全性が検討されたものであること。
-
-
8.6 マラリア流行地域への旅行者が本剤を予防に使用する際には、第一の予防はマラリア媒介蚊による刺咬を防ぐことであること、防虫スプレーや肌を露出しない服装や防虫剤を染み込ませた蚊帳の使用も効果があるとされていることを説明し、注意を促すこと。
慎重投与
-
9.1 合併症・既往歴等のある患者
-
9.1.1 心臓の伝導障害のある患者
-
症状が悪化するおそれがある。
-
-
-
9.2 腎機能障害患者
-
本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。
-
-
9.3 肝機能障害患者
-
本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。
-
-
9.4 生殖能を有する者
-
妊娠する可能性のある女性には、投与中及び投与終了後3ヵ月までは避妊させること。[9.5参照]
-
-
9.5 妊婦
-
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験で、外表、内臓及び骨格の異常(ラット、100mg/kg/日)が、また、口蓋裂(マウス、100mg/kg/日)が報告されている。[2.3、9.4参照]
-
-
9.6 授乳婦
-
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。母乳中へ移行することが報告されている。
-
-
9.7 小児等
-
低出生体重児、新生児、乳児には投与しないこと。幼児、小児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。[2.2参照]
-
-
9.8 高齢者
-
減量するなど注意すること。一般に、生理機能が低下している。
-
過量投与
-
13.1 症状
-
上記の副作用が増強してあらわれる。本剤の過量投与により、めまい、頭痛、嘔吐があらわれたとの報告がある。
-
-
13.2 処置
-
少なくとも24時間、ECGでの心機能のモニター及び神経精神状態をモニターする。必要に応じ、症候に基づく集中的な、特に心血管系障害への維持療法を行う。血液透析及び血漿交換は本剤の分布容積(Vd/F、17.7L/kg)、血漿蛋白結合率(98.3%、ヒト)、ヒト赤血球分配比(1.7)から除去効果は期待できない。
-
適用上の注意
-
14.1 薬剤交付時の注意
-
14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。
-
14.1.2 本剤は、大量の水をもって服用させること。
-
その他の注意
-
15.1 臨床使用に基づく情報
-
本剤は、pH5.5以上で溶解性が低下する。制酸剤、H2-遮断薬、プロトンポンプ阻害剤等の胃内pHを上昇させる薬剤との併用により、本剤の溶解性が低下し、吸収が低下することが考えられる。
-
-
15.2 非臨床試験に基づく情報
-
15.2.1 ラットに投与した実験で、網膜変性、網膜の浮腫及び水晶体の混濁が本薬の12.5及び30mg/kg/日の用量を6ヵ月以上の長期にわたって投与することによって発現することが報告されている。[11.1.17参照]
-
15.2.2 ラットに投与した実験で、精巣上体の萎縮、変性、前立腺の萎縮及び授胎率の低下が報告されている。
-
その他の説明
-
本剤を予防目的で使用した場合、保険給付されない。
相互作用
相互作用序文
-
本剤の消失半減期は長く、血漿中及び赤血球中の濃度は緩やかに低下するため、投与終了後も他の薬剤との薬物相互作用を示す可能性は否定できない。[16.1参照]
また、本剤は肝チトクロームP-450 3A(CYP3A)により代謝されることが示唆されている。
薬物代謝酵素用語
CYP3A併用禁忌
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| キニーネ及び類似化合物キニジン、クロロキン(国内未承認)等[2.6参照] | 急性脳症候群、暗赤色尿、呼吸困難、貧血、溶血。(少なくともキニーネ投与後12時間は、本剤を初回投与しない。また、心毒性の発現が高まるために本剤投与後2週間は、キニーネの投与を慎重に行う。) | 併用投与により心臓に対して累積的に毒性を与える可能性がある。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ハロファントリン(国内未承認)[2.7参照] | 致死的なQTc間隔の延長があらわれることがある。本剤は消失半減期が長いことより投与後においてもハロファントリンの投与は避け、他の薬剤を使用すること。ただし、ハロファントリンの投与の必要がある場合は、本剤の血中濃度を考慮し、十分な間隔をあけて慎重に投与すること。 | QTc間隔延長作用の増大。 |
併用注意
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 抗不整脈剤カルシウム拮抗剤ベラパミル等β-遮断剤抗ヒスタミン剤 | 不整脈などの心血管系に障害を及ぼす可能性がある。 | QTc間隔を延長させる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| フェノチアジン系誘導体三環系抗うつ剤イミプラミン等 | 不整脈などの心血管系に障害を及ぼす可能性がある。 | QTc間隔を延長させる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 強心剤ジゴキシン | ジゴキシンの作用増強の可能性がある。 | 類似薬のキニーネにおいて、強心剤であるジゴキシンとの併用により、ジゴキシンの血中濃度が上昇する。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| アルコール(飲酒) | 幻覚、幻聴、妄想、自殺願望。 | 本剤による中枢毒性を強める可能性、あるいはアルコールの代謝阻害による急性アルコール精神病発症の可能性がある。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 経口腸チフス生ワクチン(国内未承認) | ワクチン効果を減弱させる。(本剤初回投与の少なくとも3日前までに接種のこと。) | 腸チフス菌の増殖阻害。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 抗てんかん剤バルプロ酸等 | 抗てんかん剤の作用を減弱させる。 | 抗てんかん剤の半減期を短縮させる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 狂犬病ワクチン(HDCV)(国内未承認) | ワクチン効果を減弱させる可能性がある。(HDCVは、本剤予防投与開始前に皮内投与療法の3回の投与を終了させるために、少なくとも旅行の1ヵ月前に皮内投与療法が開始されなければならない。このスケジュールができなければ、筋注療法を行わなければならない。) | 狂犬病ワクチンに対する免疫応答の阻害の可能性がある。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| CYP3A4酵素阻害作用を有する薬剤シメチジンイトラコナゾールリトナビルマクロライド系抗生物質グレープフルーツジュース等 | 併用により本剤の血中濃度又は併用薬剤の血中濃度が変動するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。 | 本剤は肝チトクロームP-450 3Aにより代謝されることが示唆されているため、相互に影響を受ける可能性が考えられる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| CYP3A4酵素誘導作用を有する薬剤デキサメタゾンリファンピシンフェノバルビタール等 | 併用により本剤の血中濃度又は併用薬剤の血中濃度が変動するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。 | 本剤は肝チトクロームP-450 3Aにより代謝されることが示唆されているため、相互に影響を受ける可能性が考えられる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 他の(上記以外の)CYP3A4酵素で代謝を受ける薬剤 | 併用により本剤の血中濃度又は併用薬剤の血中濃度が変動するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。 | 本剤は肝チトクロームP-450 3Aにより代謝されることが示唆されているため、相互に影響を受ける可能性が考えられる。 |
副作用
重大な副作用及び副作用用語
重大な副作用
-
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
-
11.1.1 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(0.1%未満)注)[8.4参照]
-
11.1.2 中毒性表皮壊死症(頻度不明)[8.4参照]
-
11.1.3 痙攣(頻度不明)
-
11.1.4 錯乱(頻度不明)[8.4参照]
-
11.1.5 幻覚(0.1%未満)注)
-
11.1.6 妄想(頻度不明)
-
11.1.7 肺炎(頻度不明)
-
11.1.8 肝炎(頻度不明)
-
11.1.9 呼吸困難(0.1%未満)注)
-
11.1.10 循環不全(頻度不明)
-
11.1.11 心ブロック(頻度不明)
-
11.1.12 脳症(頻度不明)
-
11.1.13 呼吸抑制(頻度不明)
-
11.1.14 ショック(頻度不明)
-
11.1.15 ミオパシー(頻度不明)
-
11.1.16 視野欠損(頻度不明)
-
11.1.17 網膜障害(頻度不明)[15.2.1参照]
-
注)発現頻度は、使用成績調査に基づく。
その他の副作用
-
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
| 5%以上 | 0.1〜5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 | |
| 精神神経系 | めまい | ふらつき、不眠、魔夢、傾眠、頭痛、不安、関節痛、筋肉痛、振戦、健忘、平衡障害 | 感情不安定、異夢、抑うつ状態 | 異常感覚、落ち着きのなさ、協調異常、筋痙直、行動障害、神経症、睡眠障害、精神病様症状、ニューロパシー、パニック発作、偏執反応、末梢神経障害、末梢性運動障害、無気力 |
| 感覚器 | 視力障害、耳鳴、聴力低下 | 前庭障害、霧視 | ||
| 消化器 | 下痢、嘔気、食欲不振、腹痛、胃部不快感、嘔吐、便秘、腹部膨満 | 胃痛、潰瘍性口内炎、消化不良 | 歯肉腫脹、舌浮腫、唾液増加 | |
| 循環器 | 心悸亢進 | 期外収縮、高血圧、徐脈、心房細動、低血圧、頻脈、不整脈、房室ブロック | ||
| 血液 | 白血球減少、血小板減少 | 好酸球上昇、白血球増多、フィブリノーゲン上昇 | ||
| 過敏症 | じん麻疹、発疹、そう痒 | 多形紅斑、潮紅 | ||
| 肝臓 | AST上昇、ALT上昇 | LDH上昇 | LAP上昇、TTT上昇、ZTT上昇 | |
| その他 | 倦怠感、疲労、脱力感、発熱、胸痛、悪寒、顔面浮腫 | 脱毛、鼻出血 | BUN下降、CK上昇、アキレス腱炎、関節炎、血沈上昇、失神、多汗、トリグリセリド上昇、無力 |
-
注)発現頻度は使用成績調査に基づく。
薬価
メファキン「ヒサミツ」錠275 766.2円/錠
m3.comにご登録済の方
薬剤名検索
薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社
・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。
・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。

 同薬効薬剤
同薬効薬剤
