- m3.comトップ
- > DI Station
- > 液体窒素
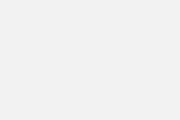
効能・効果
-
○気化設備を用いて気化し,日本薬局方窒素として使用する。
-
○注射剤の製造に際し,酸化防止のための不活性ガスとして使用する。
用法・容量
-
気化設備を用いて気化し,日本薬局方窒素として使用する。
注意事項
重要な基本的注意
-
8.1 使用に当たっては,必ずガス名を「医薬品ラベル等」で確認すること。
-
8.2 窒素過多の空気を吸入した場合,軽い眩暈・頭痛・手足のしびれ等の酸欠に伴う症状を呈することがある。このような場合は,清浄な空気の場所に移し,しばらく安静にさせること。
-
8.3 高濃度の窒素を吸入すると意識を失うことがある。このような場合は,清浄な空気の場所に移し直ちに酸素吸入又は人工呼吸を行い医師の手当を受けること。
-
8.4 合成空気を使用して高気圧療法をする際には,窒素分圧上昇による窒素酔いに留意するとともに,長時間の高気圧曝露では減圧症の危険があるので注意すること。
適用上の注意
-
14.1 薬剤調整時の注意
-
14.1.1 容器のバルブは静かに開閉する。
-
14.1.2 容器は粗暴な取扱いをせず,転倒・転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止するために,安定した床に倒れないように転倒防止措置をして立てて使用する。
-
14.1.3 ガスの使用は超低温容器から直接使用しないで,気化設備を経て使用する。
-
14.1.4 調整器及び圧力計等は,窒素用のものを使用する。
-
14.1.5 液体窒素の温度は,−196℃と極めて低温であるため,凍傷等起さぬように特に注意する。
-
14.1.6 液体窒素を建物内で放出してはならない。酸欠の危険性があるので,換気に十分注意する。
-
14.1.7 液体窒素は,気化すると約700倍の体積になるため,液を密閉状態にしないよう特に注意する。
-
14.1.8 液体窒素を取扱うときは凍傷又は傷害防止のため革手袋を着用する。
-
14.1.9 配管その他の解氷は常温で行う。
-
14.1.10 超低温容器の圧力制御装置及び安全弁,破裂板にみだりに触れない。
-
14.1.11 使用後は容器バルブを必ず閉める。
-
取扱上の注意
-
20.1 消費上の注意
-
20.1.1 設備の使用開始時及び使用終了時に異常の有無を点検するほか,1日に1回以上設備等の作動状況を点検するとともに定期的にガス濃度,圧力及び気密を点検する。もし,異常があるときは,設備の補修等の危険防止措置を講じる。
-
-
20.2 ガス漏洩時の注意
-
20.2.1 容器からガス漏れのある場合は,直ちにバルブを閉じてガスの使用を中止する。
-
20.2.2 容器安全弁(破裂板)からガスが噴出した場合は,容器から離れ換気を良くし,販売店に連絡する。
-
-
20.3 貯蔵上の注意
-
20.3.1 定置式超低温液化ガス貯槽の場合
-
(1)標識類は常にきれいな状態にしておく。
-
(2)貯槽の周辺の整理整頓を心掛ける。
-
(3)バルブの開閉状態は,常に「開」,「閉」を表示板で表示する。
-
(4)安全弁の元弁は常に全開の状態を維持し,ハンドルは回り止めを施し,封印する。
-
(5)超低温液化ガスを取扱う時は,常に凍傷又は傷害防止のため,革手袋を着用する。
-
(6)設置場所には関係者以外の立入りを禁止する。
-
-
20.3.2 可搬式超低温液化ガス容器の場合
-
(1)通風良好な状態を保つ。
-
(2)容器は粗暴な取扱いをせず,転倒,転落等による衝撃及びバルブの損傷を防止するために,安定した床に倒れないように転倒防止措置をして立てて置く。
-
(3)容器は,湿気水滴等による腐食を防止する措置を講じる。
-
・容器置場は,錆・腐食を防止するため,水分を浸入させないようにして,腐食性物質を近くに置かない。
-
・水分,異物等の混入による腐食等を防止するため,使用済みの容器でも,容器のバルブは必ず閉めておく。
-
-
(4)容器置場は必ず換気を図る(酸欠防止のため)。
-
(5)容器は「高圧ガス容器置場」であることを明示した所定の場所に,保管する。
-
・容器は,充
てん 容器と使用済み容器を区分して置く。 -
・種類の異なるガスの容器は区分して置く。
-
・容器置場には作業に必要な用具以外のものは置かない。
-
・容器置場には関係者以外の立ち入りを禁止する。
-
-
-
-
20.4 移送時の注意
-
20.4.1 容器は,直射日光を避け固定して安全に運搬する。
-
その他の説明
-
本剤は保険給付の対象とならない(薬価基準未収載)。
相互作用
副作用
薬価
液体窒素
m3.comにご登録済の方
薬剤名検索
薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社
・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。
・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。

 同薬効薬剤
同薬効薬剤
