- m3.comトップ
- > DI Station
- > アーゼラ点滴静注液100mg 他
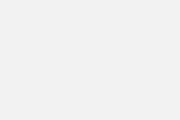
警告
-
本剤の投与は、緊急時に十分に対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して、十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。
-
アナフィラキシー、発熱、悪寒、発疹、疼痛、咳嗽、呼吸困難、気管支痙攣、血圧下降、徐脈、心筋梗塞、肺水腫等のinfusion reactionが認められている。Infusion reactionは投与回数にかかわらず投与開始後3時間以内に多く認められるが、それ以降でも発現が報告されている。また、infusion reactionにより本剤の投与を中断後に再開した場合にもinfusion reactionが再び認められているので、本剤投与中はバイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数等)のモニタリングや自他覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分観察すること。
Infusion reactionがあらわれた場合には、本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。(<用法及び用量に関連する使用上の注意>、「2.重要な基本的注意」及び「4.副作用(1)重大な副作用」の項参照) -
B型肝炎ウイルスの再活性化により肝不全に至り死亡した例が報告されている。本剤の治療期間中又は治療終了後は、肝炎の増悪、肝不全が発現するおそれがあるので、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。(「1.慎重投与」、「2.重要な基本的注意」及び「4.副作用(1)重大な副作用」の項参照)
禁忌
-
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
効能・効果
-
再発又は難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病
用法・容量
-
通常、成人には週1回、オファツムマブ(遺伝子組換え)として、初回は300mg、2回目以降は2000mgを点滴静注し、8回目まで投与を繰り返す。8回目の投与4〜5週後から、4週間に1回2000mgを点滴静注し、12回目まで投与を繰り返す。
注意事項
重要な基本的注意
-
本剤点滴静注時のinfusion reactionとして、発熱、発疹、疼痛、咳嗽等が高頻度に報告されており、約半数の患者で複数回のinfusion reactionが報告されている。また、2回目以降の投与時に初めてinfusion reactionが発現したとの報告がある。患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置(抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤の投与等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。(【警告】、<用法及び用量に関連する使用上の注意>及び「4.副作用(1)重大な副作用」の項参照)
-
抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤及び副腎皮質ホルモン剤の前投与を行った患者においても重篤なinfusion reactionが発現したとの報告があるので、患者の状態を十分に観察すること。(【警告】、<用法及び用量に関連する使用上の注意>及び「4.副作用(1)重大な副作用」の項参照)
-
B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者(HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性)において、本剤の投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。本剤の治療開始後及び治療終了後は、継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。(【警告】、「1.慎重投与」及び「4.副作用(1)重大な副作用」の項参照)
-
不整脈や狭心症等の心機能障害を合併する患者又はその既往歴のある患者に投与する場合には、投与中又は投与直後に心電図、心エコー等によるモニタリングを行うなど、患者の状態を十分に観察すること。
-
咽頭扁桃、口蓋扁桃部位に病巣のある患者で、抗CD20モノクローナル抗体製剤の投与により、炎症反応に起因する病巣の一過性の腫脹がみられ、病巣腫脹により呼吸困難をきたしたとの報告がある。このような症状が発現した場合には、副腎皮質ホルモン剤を投与するなど、適切な処置を行うこと。
-
本剤の治療中より末梢血リンパ球の減少があらわれ、治療終了後も持続すること、また免疫グロブリンが減少した例が報告されていることなど、免疫抑制作用により細菌やウイルスによる感染症が生じる又は悪化する可能性があるので、患者の状態を十分観察すること。感染症が生じた場合には適切な治療を行うこと。
慎重投与
-
肺機能障害のある患者又はその既往歴のある患者〔投与中又は投与直後に気管支痙攣や低酸素症を伴う急性の呼吸器障害があらわれ、肺機能を悪化させるおそれがある。〕
-
肝炎ウイルスの感染又は既往を有する患者〔B型肝炎ウイルスの再活性化により肝炎があらわれるおそれがある。(【警告】、「2.重要な基本的注意」及び「4.副作用(1)重大な副作用」の項参照)〕
-
心機能障害のある患者又はその既往歴のある患者〔投与中又は投与後に不整脈、狭心症等を悪化又は再発させるおそれがある。〕
-
感染症(敗血症、肺炎、ウイルス感染等)を合併している患者〔免疫抑制作用により病態を悪化させるおそれがある。〕
-
重篤な骨髄機能低下のある患者〔好中球減少及び血小板減少を増悪させ重篤化させるおそれがある。〕
-
降圧剤による治療中の患者〔本剤投与中に一過性の血圧下降があらわれることがある。〕
適用上の注意
-
調製時
-
目視による確認を行い、変色している場合は使用しないこと。
-
希釈液として生理食塩液以外は使用しないこと。
-
本剤はたん白製剤であるため、振盪しないこと。
-
希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後の残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。
-
-
投与時
-
本剤の投与は点滴静注のみとし、急速静注、静脈内大量投与はしないこと。
-
他剤との混注はしないこと。
-
-
投与速度
-
初回投与時
<用法及び用量に関連する使用上の注意>の記載に従って、4.5時間以上かけて投与すること。
-
2回目以降の投与時
直近の投与時に重度の副作用が発現しなかった場合には、<用法及び用量に関連する使用上の注意>の記載に従って、4時間以上かけて投与すること。
-
その他の注意
-
臨床試験で抗オファツムマブ抗体の陽性例が報告されている。
相互作用
併用注意
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 生ワクチン又は弱毒生ワクチン | 接種した生ワクチンの原病に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行うこと。 | ワクチン接種に対する応答が不明であり、また、生ワクチンによる二次感染が否定できない。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 不活化ワクチン | ワクチンの効果を減弱させるおそれがある。 | ワクチン接種に対する応答が不明であり、また、生ワクチンによる二次感染が否定できない。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 免疫抑制剤 | 発熱などの感染症(細菌及びウイルス等)に基づく症状が発現した場合には、適切な処置を行うこと。 | 過度の免疫抑制作用による感染症誘発の危険性がある。 |
副作用
副作用発現状況の概要
-
国内第I相試験、日本及び韓国で実施した第I/II相試験の日本人の評価症例15例中全例(100.0%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは、infusion reaction15例(100.0%)、好中球減少、白血球減少各10例(66.7%)、血中乳酸脱水素酵素増加7例(46.7%)であった。(承認時)
-
海外で実施した第II相試験の評価症例223例中149例(66.8%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは、infusion reaction111例(49.8%)、感染症44例(19.7%)、好中球減少34例(15.2%)であった。(承認時)
-
副作用の頻度については、海外で実施した第II相試験の結果に基づき算出した。なお、この臨床試験以外から報告された副作用については頻度不明とした。
重大な副作用及び副作用用語
重大な副作用
-
Infusion reaction(49.8%)
アナフィラキシー、発熱、悪寒、発疹、疼痛、咳嗽、呼吸困難、気管支痙攣、血圧下降、徐脈、心筋梗塞、肺水腫等を含むinfusion reactionがあらわれることがあり、また海外では死亡に至った例も報告されている。患者の状態を十分に観察し、重篤なinfusion reactionが認められた場合には本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。(【警告】、<用法及び用量に関連する使用上の注意>及び「2.重要な基本的注意」の項参照)
-
腫瘍崩壊症候群(0.4%)
腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。
-
進行性多巣性白質脳症(PML)(0.4%)
進行性多巣性白質脳症(PML)があらわれることがあるので、本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察すること。意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等の症状があらわれた場合には、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
B型肝炎ウイルスによる劇症肝炎、肝炎の増悪(頻度不明)
B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎又は肝炎があらわれることがあるので、肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、直ちに抗ウイルス剤を投与するなど適切な処置を行うこと。(【警告】、「1.慎重投与」及び「2.重要な基本的注意」の項参照)
-
肝機能障害、黄疸(0.9%)
AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、ビリルビン上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
汎血球減少(頻度不明)、白血球減少(2.2%)、好中球減少(発熱性好中球減少症を含む)(15.2%)、貧血(5.8%)、血小板減少(1.8%)
重篤な血球減少があらわれることがあり、好中球減少については、本剤の最終投与から4週間以上経過して発現する例が報告されている。本剤の治療期間中及び治療終了後は定期的に血液検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には休薬等の適切な処置を行うこと。
-
感染症(19.7%)
細菌、真菌、あるいはウイルスによる重篤な感染症(敗血症、肺炎等)があらわれることがあるので、本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
間質性肺炎(頻度不明)
間質性肺炎があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
心障害(頻度不明)
心不全、心筋梗塞、肺水腫、心筋症等があらわれることがあるので、これらの症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(頻度不明)
中毒性表皮壊死融解症等の重篤な皮膚障害があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
腸閉塞(頻度不明)
腸閉塞があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
重篤な腎障害(頻度不明)
腎不全等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察すること。尿量減少、血清クレアチニンやBUNの上昇が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
血圧下降(頻度不明)
一過性の血圧下降があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
重大な副作用
-
消化管穿孔
抗CD20モノクローナル抗体製剤を投与された患者で消化管穿孔が報告されている。観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
-
可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状
抗CD20モノクローナル抗体製剤を投与された患者で可逆性後白質脳症症候群(症状:痙攣発作、頭痛、精神症状、視覚障害、高血圧等)が報告されている。また、治療終了後6ヵ月までの間に、失明、難聴等の視聴覚障害、感覚障害、顔面神経麻痺等の脳神経障害が報告されている。患者の状態を十分に観察し、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
その他の副作用
| 2%以上 | 2%未満 | 頻度不明 | |
| 過敏症 | − | − | 過敏症、アナフィラキシー反応(アナフィラキシーショックを含む) |
| 循環器 | − | 頻脈 | 低血圧、高血圧、動悸 |
| 呼吸器 | 咳嗽 | 咽喉頭疼痛、呼吸困難、アレルギー性鼻炎、気管支痙攣、鼻閉、低酸素症 | 胸部不快感 |
| 消化器 | 下痢、腹痛 | 悪心、嘔吐 | 食欲減退 |
| 皮膚 | − | 発疹、そう痒症、ほてり | 蕁麻疹、潮紅 |
| 神経系 | − | − | 頭痛 |
| 全身症状 | 疲労、発熱 | 悪寒、筋肉痛、無力症 | 多汗症、サイトカイン放出症候群、背部痛 |
| その他 | − | 高尿酸血症、末梢性浮腫、回転性めまい、低ナトリウム血症 | 血中乳酸脱水素酵素増加、総蛋白減少、血中アルブミン減少、血中カリウム減少 |
薬価
アーゼラ点滴静注液100mg 28904円/瓶
アーゼラ点滴静注液1000mg 280240円/瓶
評価サマリー
m3.comにご登録済の方
薬剤名検索
同薬効で処方している薬
薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社
・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。
・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。

 同薬効薬剤
同薬効薬剤

