- m3.comトップ
- > DI Station
- > フローセン
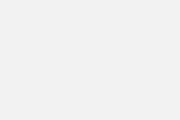
禁忌
-
以前にハロゲン化麻酔剤を使用して、黄疸又は発熱がみられた患者[重篤な肝障害があらわれることがある。]
-
本剤の成分に対する過敏症の既往歴のある患者
効能・効果
-
全身麻酔
用法・容量
-
導入
通常、ハロタン1.5〜2.0%を含む酸素又は酸素・亜酸化窒素混合ガスを吸入させる。
-
維持
通常、ハロタン0.5〜1.5%の濃度で血圧の変動に注意しながら維持する。
注意事項
重要な基本的注意
-
麻酔を行う際には原則としてあらかじめ絶食をさせておくこと。
-
麻酔を行う際には原則として麻酔前投薬を行うこと。
-
麻酔中は気道に注意して呼吸・循環に対する観察を怠らないこと。
-
麻酔の深度は手術、検査に必要な最低の深さにとどめること。
-
麻酔中は手術室内の換気を十分に行うこと。
慎重投与
-
薬物過敏症の既往歴のある患者
-
肝・胆道疾患のある患者[症状を悪化させることがある。]
-
サクシニルコリンの投与により筋強直がみられた患者[悪性高熱があらわれることがある。]
-
血族に悪性高熱がみられた患者[悪性高熱があらわれることがある。]
-
アドレナリン含有製剤を投与中の患者[併用により心筋のアドレナリンに対する感受性が亢進することが知られており、頻脈、不整脈等を起こすおそれがある。](「相互作用」の項参照)
取扱上の注意
-
【注意】
-
本剤の使用に際しては、本剤の薬理作用を熟知し、この使用に習熟した麻酔専門医により使用のこと。
-
本剤の麻酔作用は強力であるため、0.5〜3.0%の範囲で濃度を精密に加減できる気化器を使用することが望ましい。それには、本剤専用の気化器、例えばフローテックを使用するとよい。
-
本剤は気化器内に入れたままにしておくと着色することがあるので、使用後は気化器から取り出して保存すること。
-
乾燥した二酸化炭素吸収剤を用いた場合に異常発熱を呈することがあり、外国において類薬(セボフルラン)では発火したとの報告もあることから、二酸化炭素吸収剤が乾燥しないように定期的に新しい二酸化炭素吸収剤に交換し、二酸化炭素吸収装置の温度に注意すること。
-
相互作用
併用注意
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| キサンチン系薬剤 アミノフィリン水和物、テオフィリン 等 | 不整脈があらわれることがあるので併用は避けることが望ましい。 | 本剤が心筋のアドレナリンに対する感受性を亢進すること、及び左記の薬剤が副腎からのカテコールアミンの放出を促進することが考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| カテコールアミンを含有する医薬品 アドレナリン、ノルアドレナリン、ドパミン塩酸塩、ドブタミン塩酸塩 等 | 頻脈、不整脈、場合によっては心停止を起こすことがある。 本剤使用中のヒトの50%に心室性期外収縮を誘発するアドレナリン量(粘膜下投与)は2.1μg/kgと報告されている。この量は60kgのヒトの場合、20万倍希釈アドレナリン含有溶液25mLに相当する。 | 本剤が心筋のアドレナリンに対する感受性を亢進することが知られている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 非脱分極性筋弛緩剤 ツボクラリン、パンクロニウム臭化物 等 | 左記の薬剤の作用が増強するので、併用する場合には、左記の薬剤を減量すること。 | 本剤は膜安定化作用を持つため、左記の競合的遮断薬と協力的に作用する。 |
副作用
副作用発現状況の概要
-
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度については文献等を参考に集計した。(再審査対象外)
重大な副作用及び副作用用語
重大な副作用
-
原因不明の頻脈・不整脈・血圧変動、急激な体温上昇、筋強直、血液の暗赤色化(チアノーゼ)、過呼吸、ソーダライムの異常過熱・急激な変色、発汗、アシドーシス、高カリウム血症、ミオグロビン尿(ポートワイン色尿)等を伴う重篤な悪性高熱(0.1%未満)があらわれることがある。本剤使用中、
もしくは使用後に 悪性高熱に伴うこれらの症状を認めた場合は、直ちに投与を中止し、ダントロレンナトリウムの静脈内投与、 全身冷却、純酸素での過換気、酸塩基平衡の是正等適切な処置を行うこと。また、本症は腎不全を続発することがあるので、尿量の維持をはかること。 -
発熱を伴う重篤な肝障害(0.1%未満)があらわれることがある。ことに短期間内に反復投与した場合、その頻度が増すとの報告があるので、少なくとも3カ月以内の反復投与は避けることが望ましい。また、本剤と他のハロゲン化麻酔剤との間に交叉過敏症のあることが報告されている。
その他の副作用
| 0.1〜5%未満又は不明 | 0.1%未満 | |
|
麻酔中
| <低血圧、不整脈、呼吸停止> | |
|
麻酔中
| <脳脊髄液圧の上昇 注2)> | |
| 覚醒時 | 悪心、嘔吐、悪寒 | |
| その他 | 血尿 |
-
注2)脳外科手術の場合には観察を十分に行い、至適換気が維持されるよう補助あるいは調節呼吸を行うことが望ましい。
薬価
フローセン 52.8円/mL
評価サマリー
m3.comにご登録済の方
薬剤名検索
同薬効で処方している薬
薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社
・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。
・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。

 同薬効薬剤
同薬効薬剤

