- m3.comトップ
- > DI Station
- > ベハイドRA配合錠
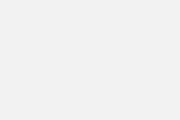
警告
-
重篤なうつ状態があらわれることがある。使用上の注意に特に留意すること。
禁忌
-
無尿の患者[無尿の患者に無効であり、また、本剤投与により高窒素血症を起こすおそれがある。]
-
急性腎不全の患者[急性腎不全の患者に無効であり、また、本剤投与により高窒素血症を起こすおそれがある。]
-
体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者[本剤のナトリウム・カリウム排泄作用により、体液中濃度が更に減少し、電解質失調を悪化させるおそれがある。]
-
うつ病・うつ状態及びその既往歴のある患者(特に自殺傾向のあるもの)[本剤に含まれるレセルピンの持つ静穏作用により症状が悪化するおそれがある。]
-
消化性潰瘍、潰瘍性大腸炎の患者[本剤に含まれるレセルピンは交感神経系の活動を抑制するため、副交感神経の活動が優位となって胃腸の蠕動運動は亢進し、胃酸分泌も増大するので症状が悪化するおそれがある。]
-
チアジド系薬剤又はその類似化合物(例えばクロルタリドン等のスルフォンアミド誘導体)、ラウオルフィアアルカロイド、カルバゾクロムに対する過敏症の既往歴のある患者
-
電気ショック療法を受けている患者[電気ショック療法を併用すると重篤な反応があらわれるおそれがある。](「相互作用」の項参照)
-
テトラベナジンを投与中の患者(「相互作用」の項参照) -
妊婦・授乳婦(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
-
テルフェナジン又はアステミゾールを投与中の患者[QT延長、心室性不整脈を起こすおそれがある。また、他の利尿剤(ループ利尿剤)でテルフェナジンとの併用によりQT延長、心室性不整脈を起こしたとの報告がある。]
効能・効果
-
高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧症
用法・容量
-
通常成人1回1〜2錠を1日1〜2回経口投与する。
-
血圧が下降し、安定化した場合は維持量として1日1〜2錠を経口投与する。
-
なお、年齢、症状により適宜増減する。
注意事項
重要な基本的注意
-
本剤は原則として単一の降圧剤治療で効果が十分でない場合に用いること。
-
本剤の利尿効果は急激にあらわれることがあるので、電解質失調、脱水に十分注意し、少量から投与を開始して、徐々に増量すること。
-
連用する場合、電解質失調があらわれることがあるので定期的に検査を行うこと。
-
夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、午前中に投与することが望ましい。
-
降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
慎重投与
-
進行した肝硬変症の患者[肝性昏睡を誘発することがある。]
-
心疾患のある高齢者、重篤な冠硬化症又は脳動脈硬化症の患者[急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮をきたし、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。]
-
重篤な腎障害のある患者[高窒素血症を起こすおそれがある。また、腎不全のある患者では血圧低下に対する順応性が不良になる。]
-
肝疾患・肝機能障害のある患者[肝機能を更に悪化させるおそれがある。]
-
本人又は両親、兄弟が痛風、糖尿病の患者[本剤は血中尿酸値、血糖値を上昇させることがあるので、痛風又は糖尿病の症状を悪化あるいは誘発させるおそれがある。]
-
下痢、嘔吐のある患者[電解質失調があらわれることがある。]
-
高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症の患者[高カルシウム血症あるいは副甲状腺機能亢進症による高カルシウム血症を悪化させるおそれがある。]
-
ジギタリス製剤、糖質副腎皮質ホルモン剤又はACTHの投与を受けている患者(「相互作用」の項参照)
-
減塩療法時の患者[低ナトリウム血症を起こすおそれがある。]
-
高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
-
乳児(「小児等への投与」の項参照)
-
交感神経切除後の患者[本剤の降圧作用が増強される。]
-
消化性潰瘍、潰瘍性大腸炎の既往歴のある患者[症状を再発させるおそれがある。]
-
てんかん等の痙攣性疾患及びその既往歴のある患者[痙攣閾値を低下させるおそれがある。]
-
気管支喘息又はアレルギー性疾患の既往歴のある患者[過敏症を増強させることがある。]
-
3.〜11.項は「重大な副作用」の項及び「その他の副作用」の項の代謝異常参照
適用上の注意
-
薬剤交付時
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]
その他の注意
-
レセルピン等のラウオルフィアアルカロイド系薬剤の使用と乳ガン発生との因果関係は未だ確立されたものではないが、乳ガンの女性を調査したところレセルピン等のラウオルフィアアルカロイド系薬剤の使用率が対照群と比較して有意に高いとの疫学調査の結果が報告されている。
-
レセルピンをラットに長期間経口投与(0.25mg/kg/日以上、103週間)したところ雄に副腎髄質の褐色細胞腫の発生増加が認められたとの報告がある
。
相互作用
併用禁忌
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 電気ショック療法 | 重篤な反応(錯乱、嗜眠、重症の低血圧等)があらわれるおそれがある。電気ショック療法を行う前には適切な休薬期間をおく。 | レセルピンは痙攣閾値を低下させると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| テトラベナジン | 相互に作用を増強することがある。 起立性低血圧等を起こすおそれがある。 | 本剤と類似した作用メカニズムを有する。 本剤の作用を増強するおそれがある。 |
併用注意
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| バルビツール酸誘導体 | 起立性低血圧を増強することがある。 | これらの薬剤の中枢抑制作用と利尿剤の降圧作用による。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| あへんアルカロイド系麻薬 | 起立性低血圧を増強することがある。 | あへんアルカロイドの大量投与で血圧下降があらわれることが報告されている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| アルコール | 起立性低血圧を増強することがある。 | 血管拡張作用を有するアルコールとの併用により降圧作用が増強されることがある。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| カテコールアミンノルアドレナリンアドレナリン | カテコールアミンの作用を減弱することがある。手術前の患者に使用する場合、本剤の一時休薬等を行うこと。 | 血管壁の反応性を低下させ、また交感神経終末からの生理的ノルアドレナリンの放出を減少させることが報告されている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ツボクラリン及びその類似作用物質ツボクラリン塩化物塩酸塩水和物パンクロニウム臭化物ベクロニウム臭化物 | これらの薬剤の麻痺作用を増強することがある。手術前の患者に使用する場合、本剤の一時休薬等を行うこと。 | 利尿剤による血清カリウム値の低下により、これらの薬剤の神経・筋遮断作用を増強すると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 降圧作用を有する他の薬剤ACE阻害剤β遮断剤ニトログリセリン等 | 降圧作用を増強するおそれがある。また、レセルピン及びβ遮断剤の副作用が増強され、徐脈、過度の鎮静等があらわれるおそれがある。降圧剤の用量調節等に注意すること。 | 作用機序の異なる降圧作用により互いに協力的に作用する。β遮断剤の場合、レセルピンがカテコールアミン枯渇作用をもつため、過度の交感神経遮断作用が起こる可能性が考えられる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ジギタリス製剤ジゴキシン等 | ジギタリスの心臓に対する作用を増強し、不整脈等を起こすことがある。血清カリウム値に十分注意すること。 | 利尿剤による血清カリウム値の低下により多量のジギタリスが心筋Na-K ATPaseに結合し、心収縮力増強と不整脈が起こる。マグネシウム低下も同様の作用を示す。また、レセルピンの交感神経終末におけるカテコールアミン遊離作用が関与すると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| キニジン | 徐脈を起こすおそれがある。 | 尿をアルカリ性にし、非解離型キニジンの割合が増し、キニジンの血中濃度が上昇することがある。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 糖質副腎皮質ホルモン剤ACTHグリチルリチン製剤 | 低カリウム血症が発現することがある。 | 両薬剤ともカリウム排泄作用をもつ。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 糖尿病用剤SU剤インスリン等 | 糖尿病を悪化(糖尿病用剤の作用を減弱)させることがある。慎重に併用すること。 | 機序は明確ではないが、利尿剤によるカリウム減少により膵臓のβ細胞のインスリン放出が低下すると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 炭酸リチウム | 振戦、消化器愁訴等、リチウム中毒を増強することがある。血清リチウム濃度に注意すること。 | 利尿剤は腎におけるリチウムの再吸収を促進し、リチウムの血中濃度を上昇させる。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| コレスチラミン | 利尿降圧作用の減弱。 | コレスチラミンの吸着作用により、本剤の吸収が阻害される。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 非ステロイド性消炎鎮痛剤インドメタシン等 | 利尿降圧作用の減弱。 | 非ステロイド性消炎鎮痛剤のプロスタグランジン合成酵素阻害作用により、腎内プロスタグランジンが減少し、水・ナトリウムの体内貯留が生じて本剤の作用と拮抗する。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ドパミン作動薬レボドパドロキシドパ等 | ドパミン作動薬の効果を減弱させることがある。 | レセルピンは脳内ドパミンを減少させ、ドパミン作動薬の抗パーキンソン病作用に拮抗すると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 抗うつ薬 | 抗うつ薬の抗うつ効果及びレセルピンの降圧効果が減弱するおそれがある。また、過度の中枢神経興奮があらわれるおそれがある。 | 抗うつ薬は主にカテコールアミン、セロトニンの再取り込み阻害により、シナプス間隙のアミン濃度を上昇させると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| モノアミン酸化酵素阻害薬 | モノアミン酸化酵素阻害薬を投与中の患者にレセルピンを追加投与することにより、興奮、血圧上昇があらわれるおそれがある。 | モノアミン酸化酵素阻害薬によりカテコールアミンの蓄積量が増え、この状態でレセルピンを投与するとカテコールアミンの遊離が増大し、反応性が高まると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 交感神経遮断薬グアネチジンベタニジン等 | 徐脈、起立性低血圧、うつ状態があらわれるおそれがある。 | 相互にカテコールアミン枯渇作用を増強すると考えられている。 |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 抗コリン性抗パーキンソン病薬トリヘキシフェニジル等 | レセルピンが抗コリン性抗パーキンソン病薬の作用を増強することがある。 | 相互に中枢神経抑制作用を増強すると考えられている。 |
副作用
副作用発現状況の概要
-
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度については文献、自発報告を参考に集計した。
-
総症例522例中、副作用が発現したのは、30例(5.7%)であった。(再評価結果)
-
以下の副作用は、頻度が算出できない副作用報告を含む。
重大な副作用及び副作用用語
重大な副作用
-
うつ状態(0.2%)
うつ状態があらわれることがあり、自殺に至るような重篤な場合があるので、患者の状態に十分注意し、悲観気分、早朝覚醒、食欲不振、陰萎又は抑制(思考、行動)等の抑うつ症状があらわれた場合には、投与を中止すること。なお、この抑うつ症状は投与中止後も数ヵ月間続くことがある。
-
再生不良性貧血(頻度不明)
再生不良性貧血があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。
-
低ナトリウム血症(頻度不明)
倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。
-
低カリウム血症(0.1〜5%未満)
倦怠感、脱力感、不整脈等を伴う低カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。
重大な副作用
-
間質性肺炎、肺水腫
類薬(ヒドロクロロチアジド)で間質性肺炎、肺水腫があらわれることが報告されているので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること
。
その他の副作用
| 0.1〜5%未満 | 頻度不明 | |
| 精神神経系注1) | めまい | 悪夢注2)、錐体外路症状、眠気、性欲減退、神経過敏、頭痛、全身振戦、知覚異常 等 |
| 血液注3) | 白血球減少、血小板減少、紫斑等の血液障害 | |
| 肝臓 | 肝炎 | |
| 代謝異常注4) | 低マグネシウム血症、低クロール性アルカローシス、血中カルシウムの上昇等の電解質失調、血清脂質増加、高尿酸血症、高血糖症 | |
| 過敏症注3) | 光線過敏症 | 発疹、顔面潮紅 等 |
| 消化器 | 口渇、下痢・軟便、食欲不振、悪心、便秘 | 胃潰瘍、嘔吐、胃部不快感、膵炎、唾液腺炎 等 |
| 眼 | 視力異常(霧視等)、黄視症 等 | |
| その他 | 鼻閉 | 倦怠感、インポテンス、全身性紅斑性狼瘡の悪化、体重増加、筋痙攣、呼吸困難 |
-
注1)観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は休薬等の適切な処置を行うこと。
-
注2)特に大量又は長期投与による場合
-
注3)観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止すること。
-
注4)定期的に検査を行い、異常が認められた場合には、減量又は休薬等の適切な処置を行うこと。
薬価
ベハイドRA配合錠 5.7円/錠
評価サマリー
m3.comにご登録済の方
薬剤名検索
薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社
・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。
・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。

 同薬効薬剤
同薬効薬剤
